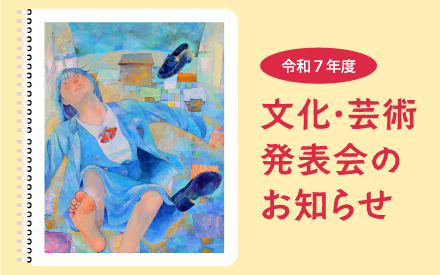お知らせ校長室から
2025.10.02
【校長便り10月】駅留(えきどめ)
校長 永井康博
「駅留」という言葉をご存じでしょうか。1970年代前半までは、個人が荷物を送る場合は、郵便局から小包(現在のゆうパック)、もしくは鉄道の駅から小荷物として発送することが一般的でした。郵便小包は荷物の大きさや重量に制限があったため、大きな物や重い物は鉄道小荷物として送ることが多かったようです。私が幼い頃、実家では「みかん」を栽培しており、収穫期になると遠方の親戚や知人に国鉄の駅から小荷物として発送していたことを覚えています。切符売り場と並んで小荷物受付窓口があり、多くの人が利用していました。今は地方の駅のほとんどが無人化され寂しい状況ですが、当時の駅は旅客だけでなく小荷物も取り扱っていたため活気がありました。ちなみに小荷物を発送する場合、「国有鉄道旅客および荷物輸送規則」によると「荷物は厳重に荷造りした上、荷受人・荷送人を書いた紙等を荷物本体に貼ると共に、同じ内容を書いた荷札をくくり付けなければならない。」などのかなり面倒な規則がありました。そして、鉄道小荷物は荷受人が近くの駅で受け取る「駅留」が一般的でした。駅に荷物が到着すると、駅から葉書や電話で連絡があり、日中(9時~17時)に受け取らなければなりませんでした。それに対し、今の宅配便は集荷にも来てくれる上、配送時間まで指定が可能で、相手の玄関先まで送り届けることができます。
運送業界に大きな変化が起きたのは、「ヤマト運輸」が1976年から宅配便のサービスを開始し、大手運送会社も追随したことです。その後、輸送にかかる時間の短縮、店舗網の拡充やコンビニからも発送できるようにしたため取扱量が飛躍的に増大していきました。その結果、鉄道小荷物は競争力を失い、1986年に廃止に追い込まれました。それに伴い、「駅留」は死語になっていきました。
もはや宅配便は我々の生活において、なくてはならない存在になっています。しかし、ドライバー不足によるサービスネットワークの維持の困難化、再配達の増加による余分な労力・エネルギー消費など、問題が山積しているのも事実です。
顧客獲得競争の過程で宅配業者が過剰とも思われるサービスを提供したことが、今に至っては自らの首をしめることになってしまったのは、皮肉なことであると思います。一方で、宅配業者の営業所やコンビニ、駅やスーパーマーケットなどに設置されている宅配ロッカーで荷物を受け取る人が増加しているというニュースを耳にしました。なんだかまるで「駅留」の復活のように感じるとともに、ドライバーの働き方改革やエネルギーの節約という観点からも良い傾向だと思います。
9月12日に今年も愛媛県武道館で運動会を実施しました。昨年の経験を活かした素晴らしい運動会になりました。多くの保護者の皆様にご来場いただき、熱い声援を送っていただいたことに心から感謝申し上げます。また、生徒の移動のために臨時列車を出していただいたJR四国様にも厚くお礼申し上げます。