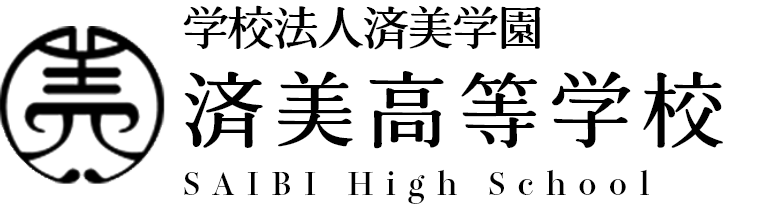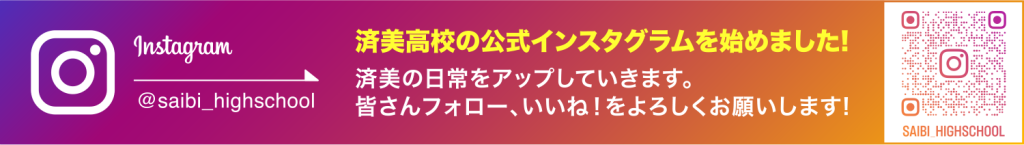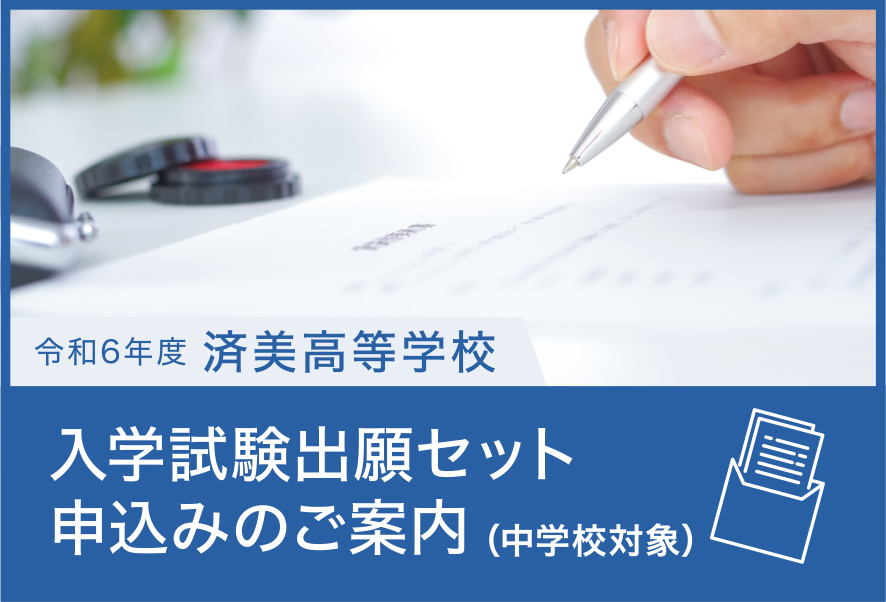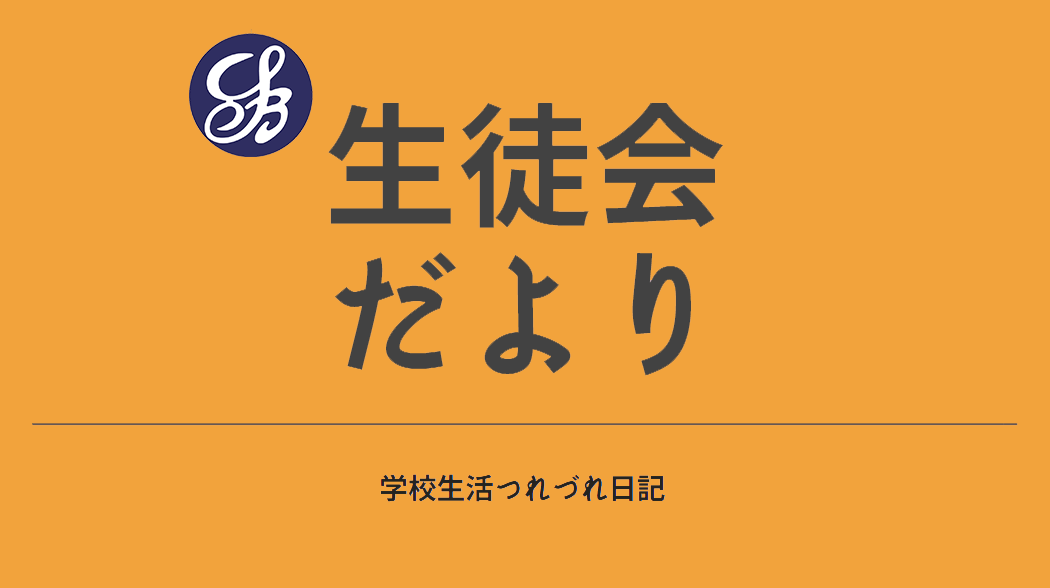学科・コース
本校は、高い学力を養う進学に特化したコースや、全国レベルを目標とする部活動に専念できる環境を備えた学業とスポーツの両立を目指すコース、音楽系大学への進学や愛媛県内で唯一の美術科を備えた音楽や美術などに専念できるコースなど、多彩なコースが特色です。
進学の済美
進学の済美! 旧帝国大学の九州大学を始め、筑波大学、東京学芸大学、岡山大学、広島大学などの難関大学に合格! 地元愛媛大学へは36名の生徒が合格しました。ACTIVEな済美生は、北海道から沖縄まで全国に進出しています。
88名
国立大学実績
949名
私立大学合格実績
36名
愛媛大学
345名
松山大学
スポーツの済美
全国トップレベルの施設・設備を有する本校は、運動部を支える施設が充実しています。県内高校最大級の体育館をはじめとして、専用陸上競技場、トレーニング室、専用野球場、専用サッカー場など、活躍する多くの生徒を支えています。
募集要項
募集要項では、募集学科・募集人員・出願期間・試験日程など、済美高等学校入試や入学に関する要項を発表致します。例年9月下旬から10月上旬までに募集要項の発表を行います。